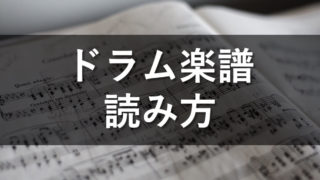あなたはこんなドラマーになっていませんか?
- スコアどおり演奏できればいいや!
- 大きな音が正義だ!
- 盛り上がる場面で音量を上げればいいんでしょ?
いずれも要注意です。
ドラマーに必要なものを3つだけあげるとしたら、リズム感とグルーヴ感、そして「ダイナミクス(音量差)」。
ロックバンドでは唯一アナログの楽器であり音量差をつけやすいのがドラム。それゆえに、ドラムがダイナミクスをつけられればバンドの表現力もワンランクアップできます。
ダイナミクスすなわち音量差がどれほど大事か、どのように変化させればよいのかを解説します。
- 音量差があるから感動する
- ダイナミクスは極端につける
- ハイハットは音量差をつけやすい
ダイナミクスとは
ダイナミクスとは、音量や音数の差をいいます。以下ではダイナミクスを音量差と定義し、曲の特定の部分を印象づけるために用いられる表現だとみなします。
ダイナミクスを実感しよう
そんなあなたは次の2本の動画をチェックしましょう。特に2本目の動画はダイナミクスによる感動を端的に味わえます。


ダイナミクスを体感してもらえましたか? 少し言葉でも説明しましょう。
ダイナミクスの重要性
さきほどの動画、もしダイナミクスがなければどのようになっていたでしょうか?
おそらくサビにかけての盛り上がりを表現できていません。サビに達した際の「ぐわっ」とも「ぶわっ」ともつかない鳥肌の立つ感覚は覚えないでしょう。
ダイナミクスによって本当に伝えたいことを表現できます。単におもしろい以上の音楽を求めるのであれば、ダイナミクスは必須です。
ダイナミクスのポイント
ではダイナミクスはどうやって表現すればよいのでしょうか?
音量差をつければよい、というのが端的な回答ですがそれではやや投げやりな気がしています。そこでダイナミクスを効果的につける方法を3点紹介します。
- 最大音量を上げる
- 最小音量を下げる
- シンバルで調整する
最大音量を上げる
もっとも盛り上げたい箇所で音量を上げる。一番わかりやすい方法かと思います。
しかし「音量を上げる」のは一筋縄ではいきません。初心者にありがちなのですが今あなたが最大音量だと思っている音はまったく最大音量ではありません。
一度でいいのでプロまたはプロに近いアマチュアドラマーの音をスピーカーを通さずに目の前で聴いてください。きっと想像をはるかに超える音量に絶句します。少なくともわたしは絶句しました。
バスドラとスネアはしっかり鳴らせればたったの一振りで人を感動させられます。冗談ではありません。それだけMAXの音量を上げることには意味があります。
最小音量を下げる
音量差を大きくするためには最大音量を上げることとその反対、すなわち最小音量を下げるのが効果的です。
ただし小さくしすぎてドラムが聴こえなくなるのも考えものです。つまりドラムが聴こえる程度の最小音量まで下げるのがベストです。
シンバルで調整する
ダイナミクスをはっきりさせる際に役立つのがシンバル、特にハイハットの音量差です。
バスドラやスネアも音量差をつけることはもちろんできますし、ある程度は上下させる必要があります。しかしどちらもビートを感じさせる程度には鳴らさなくてはなりません。
一方、シンバルは聴こえなくても問題ありません。つまり最小の音量を表現するためにはシンバルの音量を0に近しい値まで下げるのが効果的です。
最大音量を上げるのと同じような話になりますが、初心者ドラマーが想像している以上にハイハットは音量を絞って問題ありません。むしろ小さいほど引き締まって聴こえます。
静かな場面でのハイハットは、スネアやバスドラの音量を1としたときの0.1程度でも十分なほどです。
CD音源はハイハットが強調されているのでわかりにくいですが、ライブで聴くと驚くほどハイハットが小さいはずです。ライブに出かけた際は音量差をチェックしてみましょう。
ダイナミクスに関するQ&A
よくあるダイナミクスのつけかたは?
イントロ・アウトロで8割、Aメロ3割、Bメロ5割、サビ9割、間奏8割ぐらいが目安です。
もちろん曲やバンドによってまちまちなので一概には言えませんが、オーバー気味に表現したほうが伝わりやすいのは確かです。
ダイナミクスに気をつけるべき特定の場面は?
ボーカルの歌を聴こえさせたいときやギター・ベースがソロを演奏しているときは控えめに演奏するのが吉です。
ドラムが音量を抑えることでメンバーの演奏を際立たせられます。
またサビにかけての盛り上がりは少しずつ上げるイメージより、サビの直前から急激に音量を上げるイメージのほうが「ここからサビが始まるな!」感が伝わります。
思ったより表現できない
音量を上げることはさほど難しくないので、下げることに注力しましょう。
音量を上げられなくても抑える場面で抑えられていれば、相対的にサビの音量を上げられます。
あと、ダイナミクスは過剰なぐらいでちょうどいいです。「やりすぎでは…?」と思うぐらい極端にやってみましょう。案外サマになるものです。
ダイナミクスはドラマーが先陣を切る
バンドのダイナミクスはドラマーが鍵を握っています。他の楽器も音量差をつけられますがドラマーほどではありません。
ドラマーがうまくダイナミクスを表現できればバンド全体も迫力のある演奏に仕上がります。良くも悪くもドラマーの実力が試されます。
スコアどおりに演奏できたら次はスコアに表されないダイナミクスにチャレンジしましょう。
関連記事【中級者への道】
- 【第1回】録音で実力をチェック
- 【第2回】リズム感を作る
- 【第3回】他の楽器を聴く
- 【第4回】ダイナミクス(音量差)は極端に
- 【第5回】パーツごとに叩き方を変える
- 【第6回】チューニングで楽器を生かす
- 【第7回】差がつくハイハット
- 【第8回】スネアでドラムを制す
- 【第9回】バスドラを安定させる
- 【第10回】ジャストのグルーヴ
- 【第11回】4分音符を体に叩き込む
- 【第12回】裏拍を見つめ直そう