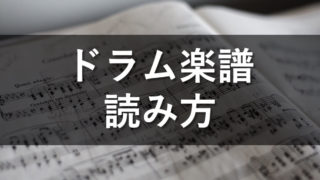あなたはこんなドラマーになっていませんか?
- ハイハットは鳴らしとけばいいや!
- ハイハットを気にしたことがなかったな
- パーツが多くてセッティングがわからない…
スネアやバスドラに気を取られてハイハットをおろそかにしていませんか? ハイハットをないがしろにしているままでは中級者にはなれません。
ハイハットは上手い人と下手な人で大きく差のつくパーツです。そんなハイハットのポイントやセッティングを解説します。
- ハイハットは上手下手がはっきり
- 唯一長さを操作できるパーツ
- セッティングで勝負が決まる
ハイハットの特徴
- 3点セットのひとつ
- 演奏中に音色を変えられる
- 長さの概念がある
ハイハットは3点セットの1つでありながら、音の長さを変えられる唯一のパーツです。ライドやフロアと同じようにビートを刻む楽器ではあるものの、音色を変えやすいのも特徴です。

ハイハットのポイント
ハイハットは音色を変えやすく長さも調整できるので繊細な表現が可能です。注意すべきポイントはいくつもありますが、まずは次の3点に注意して叩いてみましょう。
- 開く幅の調整
- アップダウンとフラット
- 閉じるタイミング
開く幅の調整
ハイハットは開く幅によって音色が大きく変わるため、細かな調整が欠かせません。
教則本では「ハイハットは指1,2本分だけ開く」というのをよく見かけます。しかし必要な表現や実力によっては大きく開くのがおすすめです。
初心者やハイハットの扱いに慣れていない人、繊細な表現を必要としない人は指1本も開かなくて問題ありません。
反対に多くの表現を必要とする人や大きく開いた音が好きな人は、指2本以上広げましょう。教則本に従う必要はありません。
アップダウンとフラット
スネアにアクセントとノンアクセント(リムにかける・かけない)があるように、ハイハットにもアクセントの有無があります。
ハイハットのふち(エッジ)を叩くのをアクセント、上(トップ)を叩くのをノンアクセントと一般的に呼びます。
8ビートで使用されるアップダウン奏法は表拍をアクセント、裏拍をノンアクセントで叩きます。
反対に、すべてをアクセントまたはノンアクセントのどちらかに統一するのがフラットです。パンクやシンプルなポップスでよく使用されます。
閉じるタイミング
音符の長さを調整できるハイハットは、閉じるタイミングにも注意を払いましょう。
ギターやベースが意識したタイミングで音を止めるように、ハイハットも音を切りたいタイミングで閉じなくてはなりません。
裏拍で叩いて表拍で音を切りたい場合は、表拍ジャストで音が止まるように左足を動かさなくてはなりません。
ハイハットのセッティング
ハイハットは2枚のシンバルを重ね合わせているため、他の楽器よりできることが多くあります。
それゆえ、セッティングで調整できるポイントも多岐にわたります。中級者はとりあえずゆるさと傾きを押さえましょう。
ゆるさのセッティング
ハイハットのすぐ上にある太いねじみたいなものを回すと、上のシンバルが固定されたりゆるくなったりします。
固定されると音がタイトになり、ゆるくなると音が伸びやすくなります。
傾きのセッティング
ハイハットのすぐ下にあるネジみたいなものを回すと、下のシンバルが傾きます。

シンバルが傾くと大きく開いてもシンバルの重なった音を出せたり、小さく開いたときは傾けていないときと重なった音を出せたりします。
ハイハットの悩みQ&A
しっかり閉められない
ハイハットはしっかり閉めないと、「チッ」ではなく「ジッ」という音がなります。
「チッ」というタイトなサウンドはかかとを上げてハイハットを踏むと演出しやすいです。
かかとを上げるとつま先に足の体重が乗りハイハットを強く閉められます。弱い力でも閉められるので筋肉のない人もぜひ試してください。
強く踏むとパカパカになる
ハイハットは力を込めて踏むと、上のシンバルがずれて上下の幅開きすぎるケースがあります。
パカパカになるのを防ぐには、高さを調整するねじの上にある部分を、チューニングキーで閉めておきましょう。

ごくたまにこの手法でも調子が悪いケースがありますが、おおよその問題はねじを閉めれば解決するはずです。
ハイハットで周りに差をつける
ハイハットは初心者と上級者の差がつきやすいパーツです。できることが多くて極めるのが難しい分、細かく調整できているドラマーはうまいとみなされます。
余裕ができたらハイハットのパーツを分解して勉強するのもおもしろいでしょう。
好きなドラマーがどのようにハイハットを使っているのかを聞き分けるのもおすすめです。
関連記事【中級者への道】
- 【第1回】録音で実力をチェック
- 【第2回】リズム感を作る
- 【第3回】他の楽器を聴く
- 【第4回】ダイナミクス(音量差)は極端に
- 【第5回】パーツごとに叩き方を変える
- 【第6回】チューニングで楽器を生かす
- 【第7回】差がつくハイハット
- 【第8回】スネアでドラムを制す
- 【第9回】バスドラを安定させる
- 【第10回】ジャストのグルーヴ
- 【第11回】4分音符を体に叩き込む
- 【第12回】裏拍を見つめ直そう