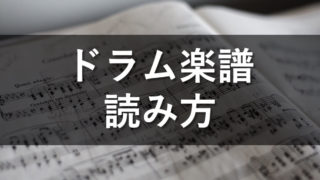あなたはこんなドラマーになっていませんか?
- スタジオのドラムをチューニングしない
- チューニングがいつもワンパターン
- 曲にあったチューニングがわからない
音程がないからか気にする人が少ない「チューニング」。オーディエンスにドラムを聴かせるという意味では、演奏と同じぐらい重要なはずなのにないがしろにしていませんか。
とはいえ敷居が高そうなのも事実です。そこでチューニングにはどのような効果があるのか、どうやったら早くチューニングできるのかを解説します。
- 完璧を目指さない
- 個人練時は3-5分で終わらせる
- バンドサウンドとも要相談
チューニングとは
チューニングは、一般的に「楽器を調律し正しい音程にすること」をさします。ただし音程の概念があまりないドラムは、音程を正しくするよりも適切な音を作るという意味合いが強いです。
以下でも、チューニングという言葉を「欲しているサウンドを作る手法」という意味で使用します。
チューニングによる変化
チューニングは次のような点を調整します。
- 音程
- サスティーン(鳴り響く音)
- 共鳴防止
- リバウンド
音程
と思うかも知れませんが太鼓にも音程は存在します。たとえばハイタムとロータムでは音程が違いますよね。太鼓にも音程の概念はちゃんとあります。
普通はしませんが、ハイタムとロータムの音程を同じにチューニングできます。太鼓も楽器である以上音程は見逃せない要素です。
サスティーン
サスティーンとは、タムやシンバルの鳴り響く音をいいます。シンバルでいうと「ジャーン」の「ーン」がサスティーンです。ちなみに「ジャ」がアタック音やアタックと呼ばれます。
スタジオのバスドラには毛布やおもりが入っているはずです。毛布やおもりはバスドラのサスティーンを短くしサウンドをタイトにする効果があります。
共鳴防止
同じ振動数を持つ物体の片方を鳴らしたとき、もう片方も音が鳴る仕組みを「共鳴」と呼びます。
太鼓同士が共鳴すること、またギターやベースの音に共鳴することがあります。
他の楽器が鳴っているときにスネアから「ジー」という音が聴こえた経験はありませんか? この「ジー」という音はチューニングで解消できます。
リバウンド
チューニングでリバウンドも調整できます。
リバウンドのためにチューニングするというケースは稀ですが、「チューニングするとリバウンドが変化する」という事実は覚えておくとよいでしょう。
きつく締めるとリバウンドは強くなり、ゆるく張ると弱くなります。
チューニングによる違い
というあなたでもわかるような音源を紹介しましょう。チューニングするにはまずは違いを知るのが大事です。
スネア
最初はスネアの違いを聞き分けましょう。音源のスネアは「カンカン」と甲高い音がします。きつめにチューニングしたハイピッチのスネアはジャズでよく用いられます。
続いてボフボフ系のスネア。デイヴ・グロールのパワーストロークが伝わるどっしりしたチューニングです。
バスドラ
バスドラの違いもチェックしましょう。メタルのバスドラは「メチメチ」と表現されるほどに高いピッチが特徴です。
続いてボソボソしているバスドラです。古めのポップスやジャズに多いです。最近のバスドラはタイトにチューニングされることが多く、下音源のようなぼやっとした音は珍しいといえます。
チューニングについてのQ&A
ライブハウスはどうチューニングすべき?
スタジオでのチューニングは基本的に好きにやっても(極端に変なのは後の人に迷惑です)、ライブハウスではあまりチューニングしないのがおすすめです。
ライブハウスではスタッフが事前にチューニングしている場合があり、あらかじめチューニングされたサウンドがPA的に編集しやすいケースもあります。
状況をみてチューニングすべきか判断しましょう。
チューニングを短時間で終わらせたい
そもそも、重要なとき以外のチューニングはだいたいでOKです。自分が違和感なければ問題ありません。
それでも短縮したい場合は、チューニングキーを2本所持して両手でチューニングするという裏ワザがあります。
また、トルクキーで機械的にチューニングするのもおすすめです。トルクキーなら一定の締り具合に統一できるためチューニングに慣れていない方でも扱いやすいです。
チューニングの基礎は押さえよう
チューニングは100%マスターしなくてもOK。もちろん完璧にこしたことはありませんが、チューニングだけに凝って肝心の演奏が伴わないのは問題です。
とはいえ、チューニングのやり方は無数にあり研究し始めると奥の深さにきっと気づくはずです。おもしろいですよ。
関連記事【中級者への道】
- 【第1回】録音で実力をチェック
- 【第2回】リズム感を作る
- 【第3回】他の楽器を聴く
- 【第4回】ダイナミクス(音量差)は極端に
- 【第5回】パーツごとに叩き方を変える
- 【第6回】チューニングで楽器を生かす
- 【第7回】差がつくハイハット
- 【第8回】スネアでドラムを制す
- 【第9回】バスドラを安定させる
- 【第10回】ジャストのグルーヴ
- 【第11回】4分音符を体に叩き込む
- 【第12回】裏拍を見つめ直そう