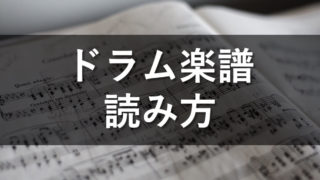あなたはこんなドラマーになっていませんか?
- 常に全力で叩く!
- 盛り上がる場面では全パーツMAX音量!
- ハイハットは鳴っててなんぼ!
前回の記事では一曲とおしての音量差を解説しましたが、今回はドラムのパーツ別による音量差を解説します。
https://musicamusik.com/post/159/
ドラムはギターやベースと違い、いくつものパーツを同時に鳴らします。そのため何も考えずに叩いていると複数の音が主張されてまとまりのないドラムが誕生します。
ごちゃごちゃしたドラムを予防するのがパーツごとに叩き方を変えるテクニックです。テクニックの重要性やコツを見ていきましょう。
- スネアとバスドラでビート作り
- ハイハットで音量に変化を
- 結局はケースバイケース
パーツごとに叩き分ける理由
ドラムはスネアやバスドラ、ハイハット、タム、シンバルと多くのパーツから構成されています。パーツは音色も音程も異なり、相対的に鳴りやすい楽器・聴こえやすい楽器とその反対の楽器があります。
また、大きく鳴らしたい楽器とそうでない楽器があります。スネアやバスドラはビートを感じさせる大黒柱的存在ですが、ハイハットやタムは飾り付けに過ぎません(暴論)。
まとめると、鳴りやすい楽器や聴こえやすい楽器、大きく聴こえさせたい楽器を鳴らし分けるために、パーツによる叩き分けが必要だというわけです。
パーツによる音量差【例】
では実際のバンドでチェックしてみましょう。
RYDEEN / YMO
1本目の音源はYMOさんのRYDEENです。ハイハットが抑えられ、スネアやバスドラが強調されていることに気づくでしょう。
YMOさんはハイハットの音量を落とすことでメリハリをつけ、スネアとバスドラを強調することでビートを目立たせています。
彼らのように音数の多いバンドは、ビートの基本となるスネアとバスドラを押し出し、ビートとあまり関係のないハイハットたちをおとなしくさせてまとめています。
駆け抜けて性春 / 銀杏BOYZ
2本目の音源は銀杏BOYZさんの駆け抜けて性春です。曲全体をとおして騒がしい演奏を受けませんか(間奏で静かになる箇所がありますが、ここでは割愛)。
彼らはパンクの要素が強いためパワフルさが必要です。ゆえにスネアやバスドラはもちろん、ハイハット、タムも大きく響かせています。
演奏をエネルギッシュに表現したければ、ハイハットも含め多くの楽器が鳴り響くように力強く叩きましょう。
パーツごとに叩き分けるポイント
ではどのパーツをどのように叩けばよいのでしょうか。パーツごとにわけて考えると次のとおりです。
- 【スネアとバスドラ】はっきり
- 【ハイハットとライド】全力の3割で十分
- 【タム】太鼓が鳴る程度
【スネアとバスドラ】はっきり
スネアとバスドラは常に一定以上の音量を鳴らしましょう。
8ビートや16ビートを叩いているときは、Aメロであってもビートを感じられる程度は音量が必要です。
Aメロ〜Bメロは太鼓を鳴らすように、サビは大きめに鳴らすように心がけましょう。
ただし大きめ = 強く叩くではありません。スネアなら肘や腕を使い、バスドラなら打面より遠い位置から踏み込み、力まずして音量をあげます。
スネアの場合はオープンリムショットでアクセントをつけるのも忘れずに。
【ハイハットとライド】全力の3割で十分
ハイハットやライドはほとんど力を込めてはいけません。力を入れなくてもきれいに鳴るからです。
シンバル類は音程が高く聴きやすい反面、耳障りにもなりやすいのが特徴です。
そのため、ビートを刻むときに叩くハイハットやライドは必要最小限の音量に抑えましょう。
サビでも4割の力でOKです。特にハイハットはオープンにすると弱い力でも鳴り響くため、他楽器を邪魔しないよう控えめに叩きます。
【タム】太鼓が鳴る程度
ビートを刻むわけでもなくシンバルでもないタムは、聴こえるけど騒がしくないレベルで鳴らします。
太鼓は一定以上の強さ(力を込めるのではなく叩き方でしっかり鳴らすという意味)で叩かなくてはなりません。
しかしスネアやバスドラよりは強調されなくてよい存在です。そのためその中間程度の音量で鳴らすのがよいです。
とはいえ初心者はタムを鳴らしきることすら難しいはず。個人的にはスネアやバスドラが負けない程度の音量までならタムもうるさくしてちょうどよいと思います。
パーツごとのQ&A
スネアやバスドラはずっとうるさいの?
スネアやバスドラでも静かにしたほうがいい場面はあります。ジャズやバラードでは優しく鳴らしましょう。ただし他の楽器がリズムと取れる程度には鳴らします。
またスネアのバズロールやゴーストノート、フラムの付属音などは静かに叩くべきでしょう。
大事なのはドラムおよび曲において何を強調すべきかを意識し、ドラムで再現することです。
ハイハットやライドはずっと静かなの?
ハイハットやライドは基本的に静かに音量をあげます。
ハイハットは開き方でライドは叩く場所で音が変化します。叩く強さより叩き方や叩く場所を選んで音を変えましょう。
パフォーマンスとして表現やパンクやメタルのような騒がしい音楽といった例外では、ハイハットを大きく叩いてもかまいません。
クラッシュはどれくらい?
クラッシュはあえて言及しませんでしたが、ケースバイケースで音量を変えてください。
大サビや激しめのロックであれば力強く鳴らし、ジャズやゆったりとした曲であれば静かに鳴らすのがよいでしょう。
また、ハイハットやライドのようにリズムを刻む用法としてのクラッシュは、音を抑えたほうがバンドがすっきりします。
パーツごとの音量は楽曲で調整
曲やバンドによって音量を使い分けてください。あれこれ書きましたが、状況によりけりというのが結論です。
あえてうるさくしたほうがいい場面、抑制したほうが効果的な場面もあります。これらの特殊な状況は楽曲を耳コピするうちに発見できるでしょう。
誰かの音源を聴き込みマネする。マネして実践する。これらの繰り返しで表現の幅を広げましょう。
関連記事【中級者への道】
- 【第1回】録音で実力をチェック
- 【第2回】リズム感を作る
- 【第3回】他の楽器を聴く
- 【第4回】ダイナミクス(音量差)は極端に
- 【第5回】パーツごとに叩き方を変える
- 【第6回】チューニングで楽器を生かす
- 【第7回】差がつくハイハット
- 【第8回】スネアでドラムを制す
- 【第9回】バスドラを安定させる
- 【第10回】ジャストのグルーヴ
- 【第11回】4分音符を体に叩き込む
- 【第12回】裏拍を見つめ直そう