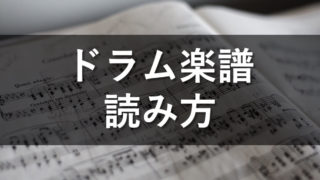あなたはこんなドラマーになっていませんか?
- 手に意識が集中してバスドラをおろそかに
- サウンドが単一的
- ベースは聴いていない
ついつい手元をがんばるあまりテキトーになってしまうバスドラ。ビートを作るはずのバスドラが不安定ではメンバーも戸惑ってしまいます。
お客さんからは見えないながら影響力の大きい影の立役者バスドラについて、意識すべきポイントや悩みの解決策を解説します。
- バスドラの安定は大前提
- ビーターでアタック音を変化
- ベースを聴こう
バスドラの特徴
- 3点セットの1つ
- 表情をつけにくい
- 1拍目によく鳴らす
バスドラはスネア・ハイハットとともに3点セットとして数えられるほど、ドラムセットには欠かせない存在です。
しかし、他の2点と違い真ん中しか踏めずサウンドが画一的になりやすいのが難点です。
1拍目に鳴らすことの多いバスドラ。この1拍目に鳴らすバスドラはかなり重要です。2拍目以降はバンドメンバーがバラバラに動くとしても、1拍目は大抵の場合音が合います。
つまり、タイミングが合うはずの1拍目(バスドラ)が不安定だとそれ以降の拍も期待ができません。そのため、バスドラが安定して鳴っているかどうかはバンド全体に関わる問題です。

バスドラのポイント
サウンドの変化に乏しいバスドラは、同じ音を安定して出せること・確実に聴こえることが重要です。
バスドラがしっかり鳴っているか、ベースと音色がかぶっていないかはよく注意しましょう。
バスドラを鳴らしきる
スネアにも言えますが太鼓をを鳴らしきるのはかなり難しいです。初心者の99%は鳴らせていないでしょう。
「こんなに大きな音が出るの!?」というレベルで鳴らさないと、バスドラを鳴らしきれいているとはいえません。
不安であれば腕の立つ先輩かドラム教室の講師に見てもらいましょう。先生役の人が実力不足だと話になりませんが…
ベースと音域をかぶらせない
バスドラはビートを刻むパーツであるため、メンバーやお客さんが確実に聴こえていなくてはなりません。
しかしベースと音域が重なっていてはせっかくのバスドラも意味がありません。
バスドラとベースは同じタイミングで鳴るとバンドに安定感をもたらしますが、サウンドまで同じにする必要はありません。
もし音域が重なってしまった場合にはベースに調整してもらいましょう。チューニングやビーターで音色を少しは変えられますが大きな変化は期待できないためです。
ビーターで音に変化
バスドラはチューニングで音色を変えるほか、ビーターでも変化をつけられます。
ビーターは素材や形によってサウンドが変わります。ビーターによっては特定のジャンルで必須とされるタイプすらあります。
| 素材 | 特徴 |
|---|---|
| フェルト | やわらかい音。優しめの音。 |
| プラスチック | やや硬めの音。アタックが強め。 |
| ウッド | 硬い音。アタックが強くメチメチ鳴る。 |
| 形 | 特徴 |
|---|---|
| 球 | 安定した音。やや柔らかい。 |
| 平面 | アタックが強めの音。 |
最初にビーターを買うのであればフェルトとプラスチックの2Wayビーターがおすすめです。多くの種類を買わなくてもサウンドを使い分けられます。
通称赤りんごと呼ばれる下のビーターは、独特の音が鳴ると評判です。メチメチしています。
バスドラについてのQ&A
ダブルやトリプルが安定しません
ダブルやトリプルの踏み方はひととおりではありません。自分にあった方法が他にないか、違う踏み方も試してみましょう。
また、ペダルのスプリングに頼りすぎている可能性があります。バスドラからの跳ね返りだけで踏めるよう、スプリング(ばね)を外して踏むトレーニングもあります。
バスドラは安定しているのが大前提
バスドラは安定してなんぼです。バスドラが安定していないのに手数ばかり増やしていては、バンド全体が安定感に欠けます。
派手なフレーズやフィルは叩ければかっこいいものの、不安定な状態でプレイしてもバンドに迷惑がかかるだけです。
身の丈にあったフレーズから挑戦しましょう。(派手なのを叩きたい気持ちもわかりますけどね…)
関連記事【中級者への道】
- 【第1回】録音で実力をチェック
- 【第2回】リズム感を作る
- 【第3回】他の楽器を聴く
- 【第4回】ダイナミクス(音量差)は極端に
- 【第5回】パーツごとに叩き方を変える
- 【第6回】チューニングで楽器を生かす
- 【第7回】差がつくハイハット
- 【第8回】スネアでドラムを制す
- 【第9回】バスドラを安定させる
- 【第10回】ジャストのグルーヴ
- 【第11回】4分音符を体に叩き込む
- 【第12回】裏拍を見つめ直そう