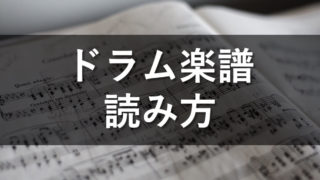第11回 第12回
【中級者への道】一覧はこちら
あなたはこんなドラマーになっていませんか?
- 裏拍って4分音符の間だよね?
- メトロノームで裏を聴く練習してます!
- 裏の感覚がわかりません…
裏拍は4分音符の間にある8分音符のことです。しかし、裏拍を表拍の間と思っているとつまずくかもしれません。メトロノームで裏を聴くトレーニングしてる人も同様です。
裏拍とはなにか、裏拍はなぜ大事なのか、裏拍の感覚はどうやったらつかめるのか解説します。これを機に裏拍を考え直しましょう。
- 白人と黒人で違う感覚
- 裏拍=4分音符の間とは限らない
- 鍛えるときは表拍・3連符と一緒に
裏拍とは
裏拍とは表拍と表拍の間にある拍です。
という説明は西洋の概念にもとづく説明です。西洋の概念がなにかは「裏拍の感じ方の違い」で解説しますが、要するに、4分音符という長さを理論的に半分に分けた長さということです。

裏拍の重要性
裏拍がなにかを解説する前に、裏拍の重要性について確認しておきましょう。
いまから紹介する音楽を次の3とおりの聴き方で聴いてみてください。3の裏拍だけカウントが難しければ、パスしても問題ありません。
- 「1,2,3,4」と表拍だけカウントする
- 「1,&,2,&,3,&,4,&」のように表拍と裏拍をカウントする
- 「&,&,&,&」と裏拍だけカウントする。
(めんどくさかったら、↑だけで終わらせても大丈夫です。)
ちゃんと3パターンそれぞれで聴いてくれましたか?
私が言いたかったのは、表拍と裏拍は役割が同じではないということです。もちろん音の長さという意味では一緒です。しかし、曲を支える表拍と曲を踊らせる裏拍は一緒ではありません。
裏拍の感じ方の違い
私がいろんな音楽を聴いていて感じたことですが、白人と黒人では裏拍に対する考え方が異なるように思えます。
白人
白人は、裏拍を表拍と表拍の間にある拍だと認識しているように感じます。
西洋人は、アカデメイアの発足に見られるように音楽を「分析」してきました。音程で言うと、オクターブ上の音(倍の周波数の音)が重なると、きれいなハーモニーになるといった具合です。
ヨーロッパの人たちは音の高さと同じように、音の長さも計測してロジカルに考えました。つまり、4分音符という概念を作り出し、裏拍はその半分の位置に存在すると理論上唱えました。
その証拠に楽譜で8分音符を2つ並べると、前が表拍で後ろが裏拍になります。同じ音符(♪)で表記されるのは、表拍と裏拍を同じものだと考えているためです。
黒人
一方黒人は、表拍で音楽を支えていながらも裏拍でリズムを取っているように感じます。
「本当か?」と思うかも知れませんね。次の2本の動画をチェックしてください。ポイントは、アーティストたちがどのような立ち方で演奏しているかです。
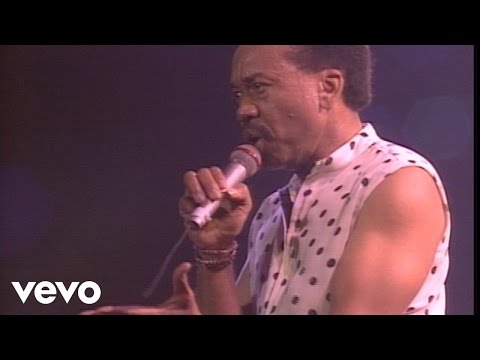

確認してもらえましたか? 参考までに白人が演奏している姿も載せておきます。

比較すると一目瞭然だと思います。黒人は踊りながらまたは体全身でリズムを取りながら演奏します。しかも裏拍をビシビシ感じています(もちろん人によって多少の差はあります)。
ではなぜ黒人は体でリズムを取りながら演奏するのでしょうか。それはリズムが体から湧いて出てくるからです。西洋のように理論ではなく、体の本能で音楽を演奏しているからです。
白人と黒人の違い
理論的に考える白人と、肉体的に感じる黒人。
どちらが正解というわけではありません。ただ音楽の自然な姿は黒人のやり方だと思います。
楽器が作られるはるか昔から踊ったり歌ったりしていた人間に、ロジックなんてありません。でも音楽はできます。
つまり体で音楽を作りだすほうが自然ではないでしょうか。そして不思議なことに、(少なくとも私の場合は)理論的なリズムのとり方より肉体的なリズムのとり方のほうが早くリズム感の習得できました。
裏拍のトレーニング
裏拍を鍛える方法は大きく2つあります。白人のような練習方法と黒人のような練習方法です。
白人のような練習法ではメトロノームを使います。メトロノームで表拍ないし裏拍をならし、その逆を感じたり声に出したりするというものです。
黒人風の練習法は音楽を使います。音楽で自然に流れている表拍と裏拍を感じます。
どちらの練習方法も下の記事で解説しているので、詳しく知りたい方はこちらをチェックしてください。

生かすも殺すも裏拍しだい
裏拍がいかに重要か、裏拍の感じ方にはなにがあるかを解説しました。
裏拍を感じるためには大きく2とおりのやり方がありますが、どちらが良いかは人によると思います。
私の場合は、黒人のようなリズムのとり方が合っていたのでその方法を中心に解説しました。
肉体的にリズムを刻む方法が優れているかのように解説してしまったかもしれませんが、どちらも試して自分にあったもので習得してください。
ただ、少なくとも両者には大きな隔たりがあるという事実だけ覚えていてもらえればありがたいです。
関連記事【中級者への道】
- 【第1回】録音で実力をチェック
- 【第2回】リズム感を作る
- 【第3回】他の楽器を聴く
- 【第4回】ダイナミクス(音量差)は極端に
- 【第5回】パーツごとに叩き方を変える
- 【第6回】チューニングで楽器を生かす
- 【第7回】差がつくハイハット
- 【第8回】スネアでドラムを制す
- 【第9回】バスドラを安定させる
- 【第10回】ジャストのグルーヴ
- 【第11回】4分音符を体に叩き込む
- 【第12回】裏拍を見つめ直そう