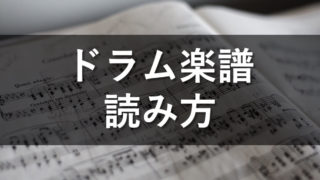あなたはこんなドラマーになっていませんか?
- とりあえず真ん中を叩いている
- オープンリムショットがうまくいかない
- 表現がマンネリ化している
スネアはドラムセットの花形で一番目立つ楽器と言えるでしょう。ビートをつくるときも盛り上げるときもアクセントを入れるときにも使える万能楽器です。
その反面、スネアの真価を発揮するには相応のテクニックが必要です。スネアの特徴はなにかどのように叩けばいいのかを確認しましょう。
- スネアを見ればスタイルがわかる
- 音程やリムで表情豊かに
- セッティングには細心の注意
スネアの特徴
- 3点セットの1つ
- 奏法が豊富
- 音の変化が多様
スネアは3点セットの1つに数えられ、バスドラと一緒にビートを生み出します。
アクセントをつけられる「オープンリムショット」、静かな雰囲気で活きる「クローズドリムショット」、無数の小さな音を重ねる「バズロール」などが特徴的です。
ハイハットやタムでも使用する「アクセント移動」や「パラディドル」と併用すると幅広い音色が引き出されます。
またチューニングすればカンカンした甲高い音や、ボフボフした野太い音など、多くの表情を見せます。

スネアのポイント
テクニックが豊富なスネアですが、次の比較的習得しやすい次の2点をとりあえずチェックしましょう。
- リムのかけ具合
- 音の高低
アクセント移動やパラディドルは日々の鍛錬でしか得られないテクニックなので、シンプルに「がんばってください!」として割愛します。
リムのかけ具合
オープンリムショットでリムを叩く際に、どれほどリムを叩くかでサウンドに変化が生まれます。
サビの中でも盛り上がる場面では深くかけて、タメる場面では浅めにかけるとメリハリがつきます。
ロールで徐々に盛り上げる場合は、前半はリムをかけないように中心近くを叩き、後半はリムをかけるために手前付近を叩くとクレッシェンドを表現できてかっこよいです。
音の高低
スネアは中央の音が一番低く、外側に近づくにつれ高くなります。
スネアを使ったフィルやロールがマンネリ化する場合は、叩く場所を変えて音程により変化をつけましょう。
GLAYさんの誘惑はド頭からスネアのみのフレーズで始まりますが、叩く場所を変化させることで表情をつけています。
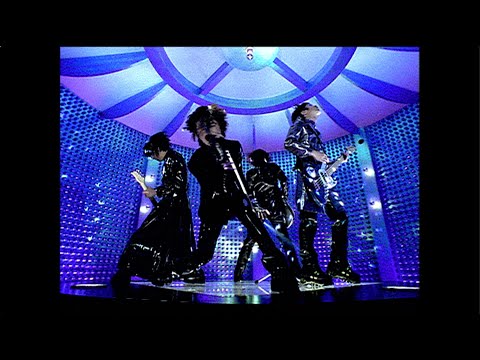
スネアのセッティング
スネアはセッティング箇所が多く、好みのセッティングを探すだけでも一苦労です。次の4点に気をつけてセットを見直しましょう。
- チューニング
- 場所
- 高さ
- 向き
チューニング
スネアのチューニングはバンドや曲によってまちまちです。楽曲に合っている音であればなんでも正解です。
ピッチの高さ、倍音やサステインの有無、ミュートにつかう道具など考える要素はたくさんあります。
どのようなチューニングがいいか迷ったときは、テンション(張り具合)を均一にしスネア本体がよく鳴る音を目指しましょう。
場所
スネアをドラムセットのどこにセットするのかは叩きやすさを考えるうえで重要です。
バスドラに近づけるのか、ハイハットの近づけるのか、椅子(スローン)に近づけるのかなどパターンは無限にあります。
高さ
スネアの打面をどれくらいにセットするかでやりやすい奏法やりにくい奏法が変化します。
椅子の高さとの兼ね合いでどれくらいにセットするのか検討しましょう。
ただしあまりに高いとリムを避けるために変な姿勢をとりかねません、傾きも考慮しながらセッティングを下げましょう。
傾き
打面の傾きはリバウンドやリムショットに影響します。
スティックと打面が水平に近いほどリバウンドを得やすいため、角度をあまりつけないのがおすすめです。
しかし角度をつけなさすぎるとリムに毎回ヒットしてしまうため微調整しましょう。
スネアについてのQ&A
いい音ってなに?
人によっていい音の基準は異なりますが、私は「太鼓本来の鳴りが引き出せているかどうか」を基準にしています。
叩き方が弱すぎると太鼓が十分に鳴りません。とはいえ力技で鳴らそうとしてもこもった音しか返ってきません。
叩いたときに太鼓の内部で空気が十分に振動するよう叩きましょう。
耳で判断できない場合は、スネアにヒットする瞬間が最速かつ力まずに叩けている状態を目指すと良いでしょう。
リムをうまくかけるには?
オープンリムショットはセッティングによって難易度を下げられます。
リムショットを叩こうとしたときのスティックの傾きと、スネアの傾きを同じ程度にセットするとリムショットさせやすいです。
スネアの高さは低めにセッティングすると腕をあまり上げなくてすむため、リムショットを楽に鳴らせます。
スネアは「人」が表れる
スネアはドラムセットの中心パーツであり、ドラマーのスタイルが垣間見える楽器です。
力強く叩くのか軽い力でしっかり叩くのか、手数を増やすのか減らすのか、ストレートに表現するのか繊細に表現するのかなど多くのバリエーションが見られます。
とはいえどのパターンもできるにこしたことはありません。簡単にでよいので、ひととおり練習しておくと演奏の幅が広がります。
関連記事【中級者への道】
- 【第1回】録音で実力をチェック
- 【第2回】リズム感を作る
- 【第3回】他の楽器を聴く
- 【第4回】ダイナミクス(音量差)は極端に
- 【第5回】パーツごとに叩き方を変える
- 【第6回】チューニングで楽器を生かす
- 【第7回】差がつくハイハット
- 【第8回】スネアでドラムを制す
- 【第9回】バスドラを安定させる
- 【第10回】ジャストのグルーヴ
- 【第11回】4分音符を体に叩き込む
- 【第12回】裏拍を見つめ直そう