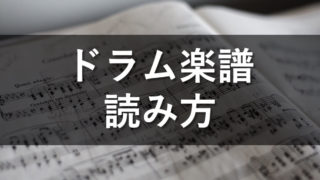- シンコペーションとは、本来弱い拍が強く、強い拍が弱くなる現象
- 通常と違うノリ方になるので、意外性が生まれる
- 「食う」「食い」ともいう
シンコペーションとは
シンコペーションとは、本来弱い拍が強く、強い拍が弱くする手法をさす。アクセントが通常の位置と異なるため、勢いや意外性が生まれる。人やジャンルによっては、「食う」「食い」とも呼ばれる。
シンコペーションの例
例をみて理解を深めていこう。
言葉で聞くより、楽譜で見て音源を聴いた方が納得できるはず。
シンコペーションなし
シンコペーションがないと次のようになる。
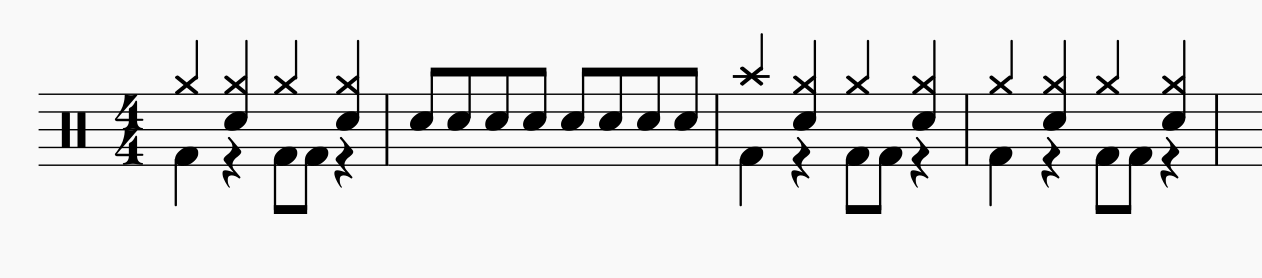
とりあえず、なしのバージョンを聴いてもらおう。
シンコペーションあり
先ほどのフレーズがシンコペーションありになると、次のように変化する。
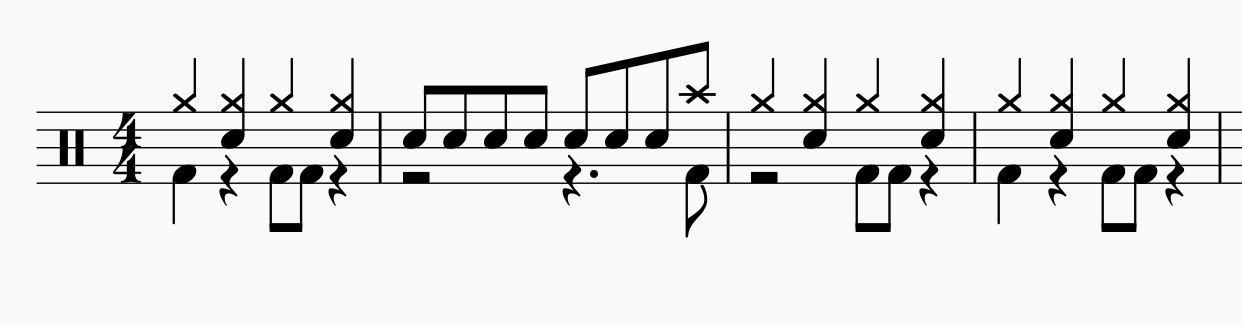
3小節目の頭にあったクラッシュシンバルが、2小節目の最後に移動している。
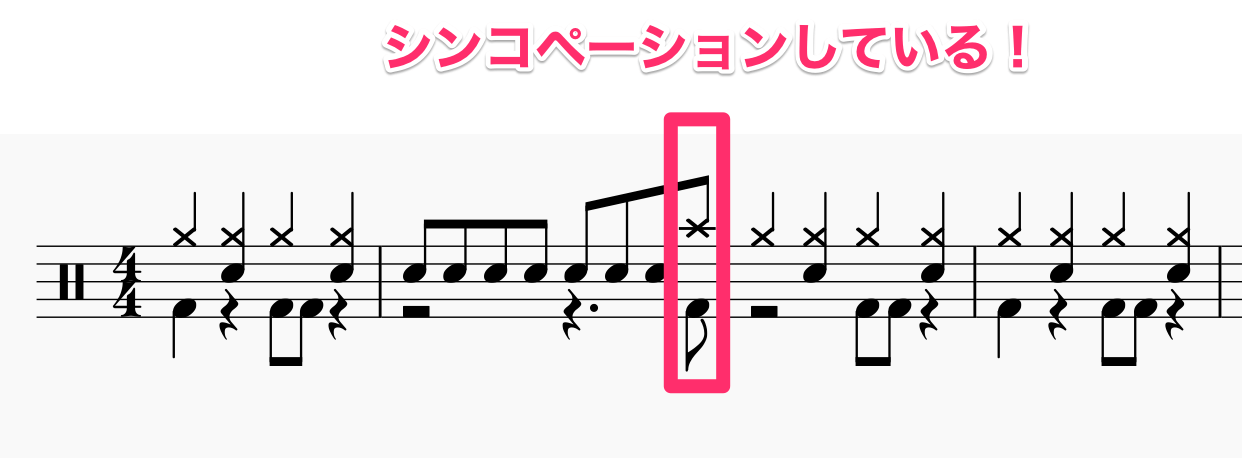
このように本来アクセントが来るべきでないところに、強調をもって来ることでドキッとさせる作用がある。
シンコペーションの曲
では実際の曲でシンコペーションが使われると、どのようになるのだろうか。
わかりやすい曲でみてみよう。
自由へ道連れ / 椎名林檎
00:55から始まるサビに注目。

サビにはわかりやすいシンコペーションが多用されている。
というあなたのためにドラムだけを抽出して聴いてみよう。
こちらがシンコペーションありのバージョン。
クラッシュの「シャーン」音の鳴っているところで、シンコペーションしている。
一方、こちらはシンコペーションなしのバージョン。
なんかいまいち物足りないのでは。
なんとなくわかったら、さっきの動画で確かめてみよう。
アフターダーク / ASIAN KUNG-FU GENERATION
アフターダークも、シンコペーションが効果的に使われている楽曲だ。

のイントロ部分でスネアがシンコペーションしている。
ここでも、簡略化したドラムでシンコペーションを確認しよう。
スネアがちょっとずれているので、「そう来るのか!」という印象をもつ。
次はシンコペーションなしのバージョン。
同じテンポでスネアが鳴っており、かなり素直に演奏しているイメージだ。
シンコペーションでアレンジ
シンコペーションについて解説したよ。
シンコペーションを意識的に使えると、曲の表情が豊かになるよ。
曲がマンネリ化するのも防止できるから、思い出したころに使ってみるとおもしろいかも。