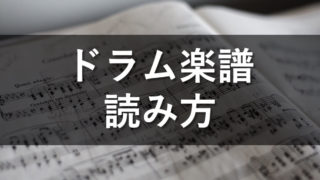走るとは
走るとは、特定のテンポより速くなっている状態ないし、速くなっていく過程をさす。「ドラムがサビで走っている」と言われたときは、サビだけテンポをあげて叩いているということ。近年の音楽は一定のテンポを保つのが主流で、テンポが変化するのはよくないとされる。
もたるとは
もたるとは、特定のテンポより遅くなっている状態ないし、遅くなっていく過程をさす。「ドラムがAメロでもたっている」と言われたときは、Aメロだけテンポを落として叩いているということ。
走る・もたるは悪くない?
走る・もたるというのは、悪い意味で使われがちです。しかしテンポの変化が必ずしも悪いわけではないんだ。
「お客さんが盛り上がっているから、少しずつ速くしよう」
「ここの部分はしっかり聴かせたいから、ゆっくり叩こう」
のように、意図的かつメンバーがとまどわない範囲でなら、テンポを変更しても問題ない。
反対に無意識的だったり、メンバーをおいてけぼりにしたりするテンポ変化は危険。
思わぬとことで曲が速くなったら、メンバーは合わせられないし、お客さんも違和感を覚える。
つまり狙いがあって速く・遅くしているなら問題はないけど、気づかぬうちにテンポが変化しているのはNGということ。
走る・もたるの原因
走る・ もたる原因はいくつも考えられる。その中でも、よく見られるものを3つだけピックアップしてみたよ。
音符の長さ意識
となっているかもしれないね。順番にみていこう。
音符にはそれぞれの長さがある。
4分音符なら4分音符の長さが、8分音符なら8分音符の長さをそれぞれ持っている。
これら音符の長さをしっかり把握するのが、「音符の長さを理解する」ということなんだ(理解して実践しなきゃいけないけど、その話は割愛)。
ドラム、特に太鼓類は音が伸びないから「長さ」という感覚がないかもしれない。
ここでいう長さとは、次の音がなるまでの時間をいうんだ。
スネアを連打しているなら、1回目と2回目の間が音の長さになるといった具合。
この「間」がどれくらいの長さなのか、把握しながら叩ければテンポはブレない。
そのための練習がチェンジアップだったりするんだ。
他の楽器
「ドラマーがテンポブレがち」というけど、本当にドラムがブレているとは限らないケースもある。
また、ドラマーが他の楽器に合わせようとしてテンポが揺れることもある。
さらに、ライブでお客さんがする手拍子に合わせてしまうことも。
これらの場合は、自分のテンポをしっかり保つのが大切。
他の人に頼りたい気持ち、合わせないといけないっていう気持ちはわかるけど、それをこらえて自分のテンポで演奏しよう。
気持ちの焦り
個人練習ではうまくいっているのに、バンドメンバーとのスタジオ練習やライブ本番だと、テンポが変化してしまう。
これもよくある現象だ。
自分ではできているつもりなのに、録音を聴くと想像以上にテンポが速くてびっくりすることあるよね。
焦りからくるテンポの変化は、慣れるしかない。
自分が緊張するときはフィルが走りがちだとか、Aメロがもたりがちだとか。
あらかじめ把握しておけば、本番でも意識してテンポをキープできる。
走り・もたりは使いどころが肝
テンポの走る・もたるについて解説したよ。
テンポの走り・もたりは状況によっては問題ないけど、使いどころには注意しよう。
最近は、クリック音(メトロノームみたいなもの)を聴いて、ライブ本番に演奏するドラマーも増えている。
クリック音を聴くなら、なおさらリズムキープできるように練習しよう。